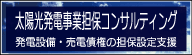不動産名義変更登記
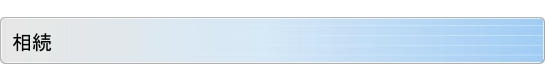
<成年後見・遺言・相続>
・元気なうちに
- 任意後見契約:本人が、最も信頼できる人として自身で選んだ人物に対して、精神上の障害によって、将来判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理を始めとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を、付与する委任契約です。この契約には任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めが必要です。
- 遺言:死後の法律関係を定めるための最終の意思表示、主なものに自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
・判断能力が低下してきたら
- 任意後見監督人選任の申立:任意後見契約の効力を生じさせます。
- 法定後見:成年後見・保佐・補助
・亡くなったら
- 相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継。注意点としては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=債務も承継されるということです。
- 遺言:遺言執行者がいる時は、遺言執行者が(いない時は相続人が)遺言の内容を実現
- 任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了
・相続
- ある人が亡くなった時、その人の権利・義務は、相続人に承継されます。遺言書の有無、法定相続、遺産分割協議等によって相続人を確定させます。
・誰が何をどのように相続するか(相続分)
- 遺言がある場合には、遺言者の最後の意思を尊重し、それに従います。
- 遺言がない場合には、通常は相続人全員で、誰が何を相続するかを決めます。(遺産分割協議)
- 何もしないのであれば、法定相続分に従って相続します。
・相続登記
- 遺産分割協議、法定相続、遺言、遺贈によって、不動産を相続・取得した場合は、不動産登記の手続が必要になります。登録免許税は、不動産の評価額の合計(100円以下切り捨て)×0.4%です。尚、2009年12月31日まで、オンラインによって法務局に申請することにより、通常の1割(最大5,000円)が軽減されます。
・負の遺産(借金)がある場合
- 被相続人の財産がプラスの財産のみとは限りません。借金しかない時などは、被相続人の財産を相続したくない場合もありえます。
- そういうときは、一定期間内に、家庭裁判所に対し、相続放棄申述の手続をすることによって、被相続人の財産を相続しないこととなります。
- 相続放棄は、法定上の相続人たる地位を放棄することなので、被相続人の残した財産が「プラス財産」「マイナス財産」であるかにかかわらず、一切相続することはありません。
・相続放棄の効果
- 相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったこととなります。
- つまり、相続人が子X・Y・Zである場合、Xのみが相続放棄をした時には、Y・Zの二人で遺産分割協議をすることとなります。
- また、相続放棄は代襲相続の原因にはなりませんので、Xに子(被相続人の孫)がいても、その子は相続人にはなりません。
・相続放棄の注意
- 相続放棄申述の手続は、自己のために相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
- なお、相続財産を処分等すると、その相続を承認したものとみなされますので、相続放棄はできません。
- また、原則として一旦相続放棄をした時には、それを撤回することはできません。
・相続放棄申述の手続
<Step 1>
- →被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。
- 必要書類
- 1. 相続放棄申述書(800円の収入印紙を貼付します)
- 2. 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
- 3. 相続人の戸籍謄本
- 4. 郵便切手(切手の種類、枚数は裁判所により異なります。)
<Step 2>
戸籍等の添付書類の収集
▼
相続放棄申述書の作成
▼
家庭裁判所へ申立て
▼
家庭裁判所からの一定の照会事項に対して回答する
▼
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
▼
家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続き終了
▼
必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付を受け、債権者に提示する。
・限定承認
- 相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないときは、家庭裁判所に「限定承認」の手続をすることができます。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。
- 要するに、相続するプラス財産の中から相続した借金を支払えばよいということです。注意しなければならないのは、債務自体が減るのではなく、その責任が減るにすぎないということです。
- 限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。
- 限定承認は、相続を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。(相続放棄と同様です。)相続財産を処分等すると、その相続を承認したものとみなされますので、限定承認はできません。
- また、限定承認をする場合には、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされて被相続人に譲渡所得税が課せられますので税務上の注意も必要です。
・相続人がいないとき
- 「相続人がいないとき」の中には、戸籍記載上の相続人が見当たらない場合や、相続人全員が相続放棄した場合も含まれます。この場合、利害関係人か検察官の請求によって、家庭裁判所は、相続財産管理人を選任します。(民法第958条第1項)
- 相続財産管理人は、相続財産を管理し、債権者や受遺者に対する催告の公告をしたり、相続人を捜索したりします。
・特別縁故者の財産分与請求
- 特別縁故者とは、(1)被相続人と生計を同じくしていた者、(2)被相続人の療養看護に努めた者、(3)その他被相続人と特別の縁故があった者がこれにあたるとされています。
- 具体的には内縁の妻(夫)や事実上の養子が挙げられます。
- 相続人が不存在の場合、特別縁故者に財産が分与されることもあります。
- 特別縁故者は、相続人捜索の公告期間(6ヶ月)の満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、特別縁故者への財産分与請求を申し立てることができます。
- 特別縁故者に対して分与をするかしないか、する場合の内容や程度は、縁故の度合い等を考慮して、家庭裁判所が判断します。
| 相続財産管理人選任 |
▼
利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)からの請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。利害関係人からの請求がない場合は、検察官がこの請求をします。
| 相続財産管理人の選任の公告 (1回目の相続人捜索の公告) |
相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の公告 この公告期間は2か月 ※公告は官報に掲載してなされる。 |
- ▼ 2か月以内に相続人が現れない場合
| 債権者・受遺者に対する債権申し出の公告(2回目の相続人捜索の公告) | 相続財産管理人の選任の公告があったあと2か月以内に相続人が現れない場合、管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して2か月以上の期間を定めて債権を申し出るよう公告する。 なお、知れたる債権者には各別に債権申出の催告をします。 |
※債権の申し出期間が経過したら債権者・受遺者への清算に移ります。
- 弁済の順位
- 1.優先権を有する債権者 2.一般債権者 3.受遺者
- 配当弁済
- 債権の申出額が相続財産を上回る場合は、配当弁済することになります。
▼ 2か月以上の債権申し出期間内に、なお相続人が現れない場合
| 相続人捜索の公告(3回目の相続人捜索の公告) | 債権申し出期間が満了後、なお相続人が現れないときは、清算と並行して、管理人の請求によって、家庭裁判所は6か月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をする。 |
この公告は、管理人又は検察官の請求により家庭裁判所が行なうものです。
この公告をなすべき時に、相続財産が全部清算されて残余財産がない場合には、この公告をする必要はないとされています。なお、前記の清算後なお残余財産があるときは、その後に現れた債権者・受遺者は、この期間内であれば弁済を受けられます。
▼ 6か月以上の公告期間が経過したとき
| 相続人不存在の確定 |
▼ 3か月以内に特別縁故者の申立てにもとづき、相続財産の全部または一部が分与される。
| 残余財産の国庫帰属 |
>> 遺産・相続コンサルティング
不動産名義変更登記
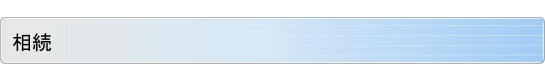
<成年後見・遺言・相続>
・元気なうちに
- 任意後見契約:本人が、最も信頼できる人として自身で選んだ人物に対して、精神上の障害によって、将来判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理を始めとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を、付与する委任契約です。この契約には任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めが必要です。
- 遺言:死後の法律関係を定めるための最終の意思表示、主なものに自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
・判断能力が低下してきたら
- 任意後見監督人選任の申立:任意後見契約の効力を生じさせます。
- 法定後見:成年後見・保佐・補助
・亡くなったら
- 相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継。注意点としては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=債務も承継されるということです。
- 遺言:遺言執行者がいる時は、遺言執行者が(いない時は相続人が)遺言の内容を実現
- 任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了
・相続
- ある人が亡くなった時、その人の権利・義務は、相続人に承継されます。遺言書の有無、法定相続、遺産分割協議等によって相続人を確定させます。
・誰が何をどのように相続するか(相続分)
- 遺言がある場合には、遺言者の最後の意思を尊重し、それに従います。
- 遺言がない場合には、通常は相続人全員で、誰が何を相続するかを決めます。(遺産分割協議)
- 何もしないのであれば、法定相続分に従って相続します。
・相続登記
- 遺産分割協議、法定相続、遺言、遺贈によって、不動産を相続・取得した場合は、不動産登記の手続が必要になります。登録免許税は、不動産の評価額の合計(100円以下切り捨て)×0.4%です。尚、2009年12月31日まで、オンラインによって法務局に申請することにより、通常の1割(最大5,000円)が軽減されます。
・負の遺産(借金)がある場合
- 被相続人の財産がプラスの財産のみとは限りません。借金しかない時などは、被相続人の財産を相続したくない場合もありえます。
- そういうときは、一定期間内に、家庭裁判所に対し、相続放棄申述の手続をすることによって、被相続人の財産を相続しないこととなります。
- 相続放棄は、法定上の相続人たる地位を放棄することなので、被相続人の残した財産が「プラス財産」「マイナス財産」であるかにかかわらず、一切相続することはありません。
・相続放棄の効果
- 相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったこととなります。
- つまり、相続人が子X・Y・Zである場合、Xのみが相続放棄をした時には、Y・Zの二人で遺産分割協議をすることとなります。
- また、相続放棄は代襲相続の原因にはなりませんので、Xに子(被相続人の孫)がいても、その子は相続人にはなりません。
・相続放棄の注意
- 相続放棄申述の手続は、自己のために相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
- なお、相続財産を処分等すると、その相続を承認したものとみなされますので、相続放棄はできません。
- また、原則として一旦相続放棄をした時には、それを撤回することはできません。
・相続放棄申述の手続
<Step 1>
- →被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。
- 必要書類
- 1. 相続放棄申述書(800円の収入印紙を貼付します)
- 2. 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
- 3. 相続人の戸籍謄本
- 4. 郵便切手(切手の種類、枚数は裁判所により異なります。)
<Step 2>
戸籍等の添付書類の収集
▼
相続放棄申述書の作成
▼
家庭裁判所へ申立て
▼
家庭裁判所からの一定の照会事項に対して回答する
▼
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
▼
家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続き終了
▼
必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付を受け、債権者に提示する。
・限定承認
- 相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないときは、家庭裁判所に「限定承認」の手続をすることができます。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。
- 要するに、相続するプラス財産の中から相続した借金を支払えばよいということです。注意しなければならないのは、債務自体が減るのではなく、その責任が減るにすぎないということです。
- 限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。
- 限定承認は、相続を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。(相続放棄と同様です。)相続財産を処分等すると、その相続を承認したものとみなされますので、限定承認はできません。
- また、限定承認をする場合には、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされて被相続人に譲渡所得税が課せられますので税務上の注意も必要です。
・相続人がいないとき
- 「相続人がいないとき」の中には、戸籍記載上の相続人が見当たらない場合や、相続人全員が相続放棄した場合も含まれます。この場合、利害関係人か検察官の請求によって、家庭裁判所は、相続財産管理人を選任します。(民法第958条第1項)
- 相続財産管理人は、相続財産を管理し、債権者や受遺者に対する催告の公告をしたり、相続人を捜索したりします。
・特別縁故者の財産分与請求
- 特別縁故者とは、(1)被相続人と生計を同じくしていた者、(2)被相続人の療養看護に努めた者、(3)その他被相続人と特別の縁故があった者がこれにあたるとされています。
- 具体的には内縁の妻(夫)や事実上の養子が挙げられます。
- 相続人が不存在の場合、特別縁故者に財産が分与されることもあります。
- 特別縁故者は、相続人捜索の公告期間(6ヶ月)の満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、特別縁故者への財産分与請求を申し立てることができます。
- 特別縁故者に対して分与をするかしないか、する場合の内容や程度は、縁故の度合い等を考慮して、家庭裁判所が判断します。
| 相続財産管理人選任 |
▼
利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)からの請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。利害関係人からの請求がない場合は、検察官がこの請求をします。
| 相続財産管理人の選任の公告 (1回目の相続人捜索の公告) |
相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の公告 この公告期間は2か月 ※公告は官報に掲載してなされる。 |
- ▼ 2か月以内に相続人が現れない場合
| 債権者・受遺者に対する債権申し出の公告(2回目の相続人捜索の公告) | 相続財産管理人の選任の公告があったあと2か月以内に相続人が現れない場合、管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して2か月以上の期間を定めて債権を申し出るよう公告する。 なお、知れたる債権者には各別に債権申出の催告をします。 |
※債権の申し出期間が経過したら債権者・受遺者への清算に移ります。
- 弁済の順位
- 1.優先権を有する債権者 2.一般債権者 3.受遺者
- 配当弁済
- 債権の申出額が相続財産を上回る場合は、配当弁済することになります。
▼ 2か月以上の債権申し出期間内に、なお相続人が現れない場合
| 相続人捜索の公告(3回目の相続人捜索の公告) | 債権申し出期間が満了後、なお相続人が現れないときは、清算と並行して、管理人の請求によって、家庭裁判所は6か月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をする。 |
この公告は、管理人又は検察官の請求により家庭裁判所が行なうものです。
この公告をなすべき時に、相続財産が全部清算されて残余財産がない場合には、この公告をする必要はないとされています。なお、前記の清算後なお残余財産があるときは、その後に現れた債権者・受遺者は、この期間内であれば弁済を受けられます。
▼ 6か月以上の公告期間が経過したとき
| 相続人不存在の確定 |
▼ 3か月以内に特別縁故者の申立てにもとづき、相続財産の全部または一部が分与される。
| 残余財産の国庫帰属 |
>> 遺産・相続コンサルティング
-
不動産名義変更登記 >相続 >遺言 >相続登記(不動産登記)